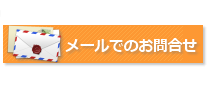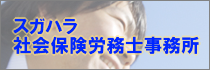就業規則には何を書けばいいの?どうやって届出するの?
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
定めがあれば記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
【絶対的必要記載事項】
① 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、
交替勤務等がある場合には就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払の方法、
賃金の締切および支払の時期、昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【相対的必要記載事項】
定めがあれば記載しなければなりませんが、言い換えると、そのようなルールが
ない場合にはわざわざ作成して記載する必要はありません。
④ 退職金の定めをする場合は、適用される従業員の範囲、退職金の決定、
計算および支払の方法、退職金の支払時期に関する事項
⑤ 臨時の賃金等(退職金を除く)および最低賃金額の定めをする場合は、
これに関する事項
⑥ 従業員に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、
これに関する事項
⑦ 安全・衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
⑧ 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
⑨ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、
これに関する事項
⑩ 表彰、制裁の定めをする場合は、その種類および程度に関する事項
⑪ 上記④~⑩のほか、当該事業場のすべての従業員に適用される定めを
する場合は、これに関する事項
尚、これらは法令による規制を受けるため、法令の基準を下回る定めをすることはできません。仮に下回る定めをしたとしても、それは法令の基準に読み替えられます。
たとえば、就業規則に「週所定労働時間は52時間とする」という条文を定めたとしても、労働基準法で“労働時間は週40時間以内”と決められているため、この就業規則の条文は無効となり、週40時間に読み替えられるというわけです。
以下、就業規則作成(変更)後の流れは次のとおりです。
1. ※従業員代表の方の意見を聴き、意見書に記入押印してもらう
↓
2. 作成(変更)した就業規則に上記の意見書を添えて労働基準監督署へ
届出する
↓
3.※従業員さんへ周知させる
※就業規則は、作成・届出だけでなく、従業員さんへ周知させて初めて効力を
発します。作成後はきちんと周知・理解してもらい、お互い就業規則を守る
ことが大切です。
※意見を聴くというのは、文字通り“意見を聴く”ことさえすればよいのであって、
その意見を内容に反映させなければならないというものではありません。